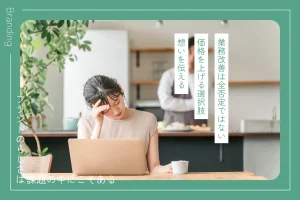規模・人数を問わず、事業には必ず「ブランドイメージ」が存在します。たとえお一人で運営されている事業であっても、それは例外ではありません。なぜなら、ブランドイメージとは一方的に作り出すものではなく、歴史や従業員、お客様との関係性を通じて自然と形成されるものだからです。
経営者が理想とするブランド像は、そのイメージのごく一部でしかなく、ブランド全体の姿ではありません。ゆえに、主観を離れた「客観的な視点」でブランドを見つめ直すことが極めて重要です。その視点を支えるのが「ブランド人格」という考え方です。
ブランド人格とは
ブランド人格とは、ブランドの内面に潜む“哲学・生き様・価値観・性格”を包括的に定義し、言語化するものです。ブランドイメージが「他者からどう見られているか」という外面的な評価であるのに対し、ブランド人格は「ブランドそのものが内包する信念・態度・人生観」です。
このブランド人格が明文化されていないと、ブランドイメージは経営者や担当者の感情的な判断に依存し、属人化してしまいます。属人化したブランドは、将来的に経営者や創業者のスタイルが変わったときに崩れやすく、一貫性が薄れてしまうリスクがあります。
ブランド人格がなぜ大切なのか?
判断基準が明確になる
ブランディングとは、様々な選択や判断に一貫性を持たせることが重要です。ブランド人格を定義することで、「このブランドらしい対応とは何か?」という軸が明確になり、迷ったときにもブレない意思決定が可能になります。
ブランドに判断を委ねるということ
ブランドに判断を委ねるといってもいきなりどうしたらいいか難しいですよね…。
ブランドに判断を委ねるというのは例えば、お仕事の中などで「こうすれば、◯◯さん喜ぶからこうしておこう!」という風に判断をするタイミングがあるかと思います。とてもこの感覚に似ているのです。
この判断を行うにはブランド人格をきっちり設定していく事が大切です。
属人性を排除し、ブランドを普遍化する
経営者一人のイメージにブランドを依存せず、歴史や関係者・顧客との共同作業によって築かれた価値を中心に据え直すことで、ブランドの普遍性が担保されます。
一貫したコミュニケーションが可能になる
メッセージやトーン、マーケティング戦略、顧客対応など、どのような状況でも“ブランドらしさ”が保たれるようになります。顧客に対しても信頼性と安心感を与えることができます。
ブランドに「判断を委ねる」とはどういうこと?
たとえば、日々の業務の中で「この対応をすれば〇〇さんが喜んでくれるだろう」という判断ができるのは、相手の人格や価値観、反応パターンを理解しているからです。それと同じように、ブランドにも「人格」を与えることで、ブランドが喜ばれる対応、ブランドらしい行動を判断できるようになります。
こうしたブランド判断は、以下のような場面で役立ちます
- 新商品の企画立案
- 顧客からの問い合わせ対応
- プロモーションや販促物のトーン
- 採用や社内の雰囲気づくり
- 危機管理やネガティブ対応の一貫性 など
ブランド人格が明確であれば、「このブランドらしい言い回し」「このブランドらしい行動」が瞬時に判断でき、現場の自律性と統一感が整います。
ブランド人格の「つくり方」── ヒアリングと言語化
「ブランド人格をつくり方」と表現していますが、正確には「ブランド人格を掘り起こし、言語化していく」作業です。これは一方的な企画ではなく、関係者の対話や過去の振り返りを通じて定義するプロセスです。
主に以下の4つの柱に沿って整理します
哲学(Philosophy)
ブランドの原点にある想いや理念、創業者の信念を探り、言語化します。「なぜこのブランドは生まれたのか?」「どんな社会課題を解決したいのか?」といった本質を言葉にします。
生き様(Way of Life)
過去の事業活動、従業員とお客様の関係、失敗・成功のストーリーなどを振り返ります。リアルな日常や人との関わりを深掘りすることで、「ブランドがどう成長してきたか」が鮮明になります。
価値観(Values)
ブランドが大切にしている価値を、具体的なエピソードをもとに可視化します。数字では見えにくい“嬉しかったできごと”“感動した瞬間”“成長を実感した体験”など、感情やエピソードから言語化していきます。
性格(Character)
哲学・生き様・価値観の結果として生まれる“性格”を定義します。もしブランドが人だったら、どんな性格?(例:誠実で温かみがある/挑戦的で革新的/頼りがいのある相談者タイプなど)
ブランド人格を明文化する流れ
ステークホルダーへのヒアリング
創業者、従業員、長年の顧客など。ブランドに関わった人々へのインタビューを通じて、価値観や想いのヒントを集めます。
事例・出来事の収集
エピソードの収集。数字ではない「ヒューマンな物語」を引き出し、ブランド価値の根っこを探ります。
要素の抽出と整理
哲学・生き様・価値観・性格に分類し、それぞれのエッセンスを言語化。ブランドの“内なる声”を言葉にします。
ブランド人格のプロトタイプ作成
「○○のようなブランド」「~のような性格」「~のような行動スタイル」という表現で、ブランド人格をドラフト化。
社内外へのフィードバック
モデル案を関係者へ共有し、「本当にこういうブランドだと共感するか?」を確認。必要に応じて修正・改訂します。
最終版の確定と共有
ブランド人格を言語化した完成形を文書化し、メッセージツールや資料などで全員に展開。一貫した基準として活用します。
まとめ
ブランド人格を言語化し、共有することは、事業の規模にかかわらず、ブランドを持続可能なものにするための基盤です。主体的かつ客観的にブランドを見つめ直し、「判断軸」を整え、一貫性のあるブランド体験を提供しましょう。